柴田侑宏 はじめての「余韻」を読む
2020.05.29
殻を割って外の世界に出てきた雛は、最初に目にしたものを親と思うらしい。
人間にもそれと同じメカニズムなのか、どんな人にも「初めて触れたもの」に対する思い入れがあり、その後の思考や行動に影響を及ぼしているという実感はどなたもあると思う。初めて買ったCD(今の子はCD買わないのか……)、初めての旅行、初めての恋、初めての大ゲンカ、初めて取れた契約、初めて書いた記事……。破り捨てたくなるような恥ずかしさと苦さが同居する。
ちなみに、人間の味覚の中で「苦味」は生存本能らしい。だから、いろんな「初めて」は苦くて、それに一生振り回されるのかもしれない。
わたしが重くて厚い宝塚歌劇の扉を開いて、今でも「親だ」と追従する人、それは柴田侑宏氏だ。彼は故人で、2019年7月に87年の生涯に幕を閉じた。2015年まで新作を書き続けていたので、1958年の入団以来、57年現役で筆を取ってきた巨匠である。
初めて観た作品はNHKの特番内『青き薔薇の軍神』(1980年 雪組公演/主演 麻実れい・遥くらら)。A&Sゴロン原作のフランスの小説を元にした木原敏江氏の少女漫画が原作だった。美しい麻実さん・遥さんに目を奪われた以上に、なぜかわたしはこの物語の虜になり、すぐさま原作の漫画を買い、しばらくして原典まで読んだ。そんな思い入れがある“初めての宝塚”、それが柴田侑宏氏である。

柴田さんの立ち位置をヅカファン的独断で解説すると、いわゆる「ベルばらブーム」の立役者である座付作家・植田紳爾氏と並んで人気の作品を残し続けてきた、いわば“宝塚の双璧”という立ち位置だ。「ベルばらブーム」とは池田理代子氏原作の少女漫画『ベルサイユのばら』を翻案したもので、宝塚ブームを起こし、一定のファンが常に支持するエンターテインメントとしての地位を確立したものであった。今でも、タカラヅカといわれればベルばらを想起する人は多いと思う。そして、今でこそ宝塚歌劇では少女漫画作品の翻案が上演されるし、いかにも少女趣味だという印象があるだろうが、当時は「少女漫画をタカラヅカで上演するなんて」と、内外から批判が起こるような“確変”だったわけである。
いつだって、どんな王道もはじめは邪道だったんだなと、思い知らされるわけである。
その「ベルばら」の人、植田紳爾さんの作風は一言でいえばスペクタクルだと思う。二枚目時代劇スター・長谷川一夫氏を演出に迎えるなど、今の宝塚の「スターシステム」の基盤を築いた。
それに対し、柴田氏の作風は「人間ドラマ」である。山本周五郎的というか、実際山本周五郎作品を多く翻案しているし、1994年上演『雪之丞変化』(雪組/主演 一路真輝・花總まり)では尾上菊五郎を演出に招いているあたり、彼の書く物語はどこまでも「日常の一部」なのである。歌舞伎の「世話物」のように庶民の話に限らず、皇族だろうが王族だろうが1人の男・1人の女として “遠い昔の遠い国、遠い身分の誰かの話”を「同じ人間の世話物」にしてしまうのが、柴田流だと受け取っている。
ちなみに、たまたまここまで紹介してきたものがいわゆる「時代劇」ばかりだけれど、『赤と黒』(スタンダールの同名小説)、『うたかたの恋』(クロード・アネの同名小説)、『チェーザレ・ボルジア』(15〜16世紀イタリアに実在した軍人。塩野七生の小説が原作)といったところで、古今東西さまざまな題材をテーマに作品を残し続けた。

そんな彼の作風を11歳のわたしが「人間ドラマだなあ」と思ったわけでは当然ない。そんな11歳ちょっと怖いと思う。
わたしがそのとき「おもしろい、もっと読みたい」と思ったのは、彼独特の最後の一文にあった。
たとえば、初見の『青き薔薇〜』の次に観たのは『あかねさす紫の花』(1995年 雪組/主演 一路真輝・花總まり)だった。のちの天武天皇となる大海人皇子と、その元妻である額田王の伝説の悲恋を題材にしつつ、主人公の大海人と彼の兄でありゆるしがたい恋敵・天智天皇との確執の予感を描く作品である。
そのラストシーンは、天智天皇の即位の祝いの席に、酩酊した大海人が乱入し、兄・天智の座に槍を突き刺すというエピソードで締め括られる。ちなみにこのエピソードは『少年少女日本の歴史2』(小学館)にも描かれているほどで、歴史的に認知されているようだ。同書ではこのエピソードは第3章に描かれ、第4章 壬申の乱(大海人と天智の子のあらそい)につながっていく。
最後の一文は、額田王が兄に刃を向けた大海人を諫めるセリフ。
額田王「ご座興が過ぎます、お静まりください……!」
これで、大海人の高笑いのまま幕が閉じた記憶がある。
この幕切れに、当時のわたしは「終わらないのに終わった」という感想を持った。誰かの一代記を書くとして、誰かが何かをなしたり、失墜したり、ともすると死んだりするところでクライマックスが訪れるのはイメージできるだろう。だが、小説やオペラなどの原作を持たない場合、柴田作品はそういう大団円を描かないところが「世話物」だなあと思う。
あくまで私たちが目にしているのは、その人の人生の一瞬のできごとであるというスタンス。実際に上記の兄弟は兄が死ぬまで目立った争いや対立はしていないようだから、その後も「まあまあ普通に生活していた」ことがうかがえるのである。
オリジナル作品でいうと「そのあとどうなったの⁉︎」の引き合いに出されやすいのは『琥珀色の雨にぬれて』(1984年花組初演)がある。許嫁のいる青年貴族が高級マヌカン・シャロンと恋に落ち、その取り巻きの青年、自身の許嫁やその兄などとの人間関係に苦悶する恋愛ドラマだ。
話はなんやかんやあって、最終的に主人公は許嫁への不貞がばれ、咎められ、それぞれ元鞘に落ち着き主人公は許嫁と結婚する。
そしてラストシーン、琥珀色の雨が降るイタリアの湖で偶然(?たぶん)2人はすれ違うこととなる。
シャロン「琥珀色の雨。まるで、美しい思い出のよう」
主人公が既に身を固めてしまった中で、上のセリフはシャロンが今共にいるパトロンに対して話した一言だった。この後テーマソングが流れ、2人は言葉を交わすことなく幕が下りるわけだけど、このあと2人は一生会わなかったのか、この再会で再燃してしまったのか議論が分かれるところである。
これが、柴田さん流とは余韻だなあと思うもう1つの理由だ。
わたしがこの作品を初めて観たのは2002年花組の春野寿美礼さんver.だった。求心力のあるスタータイプでありながら、少し疲れた演技をしていたのでそのときは「この恋は終わったんだな」と思ったが、その後2002年 匠ひびきさんver.を観て少し印象が変わった。彼女は儚げな憂いが持ち味なので、この人はまたシャロンに会いにいってしまうんじゃないか?と思った。

ちなみに、この恋は終わった派の言い分としては「琥珀はその時代の生き物を閉じ込めてしまうのだから、思い出は閉じ込めた」という。が、終わってない派のわたしは「その閉じ込めたものを今に運び、まざまざと見せつけるのが琥珀である」という主張である。
この余韻が、どんなに遠い身分の人でも、庶民でも、外国人でも日本人でも「1人のひと」として受け手に迫ってくる理由だと分析している。もちろん、クライマックスで主人公が何か人生の区切りをつける作品もある。それでも、仮に史実や原作の結末としてそれがわかりきっていてもそのありように驚いて涙してしまうような近い息づかいを感じるのが柴田作品の世界だと思う。
前回以上に長くなってしまった感がある。しかも、置いてけぼり感がないか心配である。大丈夫?ついてきてる?
結びに、余談として宝塚ファンはその鑑賞プロセスによって「3つの型」に分けられることを説明したい。
1つは「タニマチ-パトロン型」。好きな生徒(出演者)が世界の中心で、とにかくご贔屓が出ていればなんでもよいというスタンスだ。知る限り先述の「ベルばらブーム」以降は間違いなくこの型が主流で、ある意味当時の映画スターや当時のアイドルと近い存在となった。美しさに熱狂することこそ醍醐味とすれば最も王道であり、ファンクラブ活動にしても、スターシステムにしても、この消費タイプが宝塚歌劇団を支えている。
ということは、元関係者によるこちらの文献にも書いてあった。ご参考まで
元・宝塚総支配人が語る 「タカラヅカ」の経営戦略(森下信雄/2015年 角川Oneテーマ21)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321406000114/
2つめは「映画-小説型」。映画や小説のように、物語性とシーン1つひとつの美しさを大切にする。といっても高尚な純文学以外を受け付けないほどオカタイつもりはなく、話がシンプルでも粋で、会話の辻褄が合って心あざやかに見えればよいという程度だ。植田紳爾さんが1つめの立役者なら、柴田侑宏さんはこの2つめのタイプのファンの厚い支持を受け続けた。たぶん30年以上ファンを自負する人にはこのパターンが多いと思う。
わたしが最初に開けた扉はココ。だから、文学入門と冠しているのである。
3つめは「オペラ-バレエ型」。これらの舞台を鑑賞するように、演者の高いパフォーマンスを楽しみたい層は近年増えている。これは1995年初演ミュージカル『エリザベート』上演が起爆剤になったとみている。オペラやバレエも原作はよく見ると「⁉︎」とマガジンマークが飛び交うようなトンチキヒストリーが多いが、多少の話や様式美のアラよりも演者そのものの高いパフォーマンスや、それに至る努力の経緯に称賛を送りたいタイプのファンだ。
3つめのタイプは最近多い傾向といったが、実際はベルばら以前もブロードウェイ輸入ミュージカルを多数上演しており、様式美・スターシステムよりも高いパフォーマンスを追い求めていたことがうかがえる。
宝塚歌劇団の強さは実はこのバイオリズムにあり、圧倒的に支持されている王道があっても、もう1つの嗜好を否定し淘汰しないのだ。
傍目には「ベルばらブーム」の “影”に隠れたように見えるかもしれない、柴田侑宏さんの作風。そんな影の方に惹かれたというのは、編集者としてはちょっと苦い思いもあるが…
植田さんというパイオニアの影に、柴田さんという名匠あり。
わたしは、この正解が1つじゃなく、盛衰の繰り返しがどこまでも続いていく余韻を感じるタカラヅカが好きなのである。


























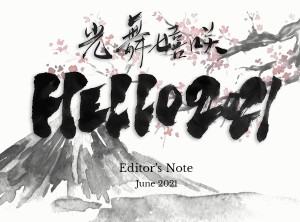


ななしましゅうこ/1986年生まれ、福岡県出身。立命館大学文学部学際プログラム(現・文化芸術専攻)卒業。某放送協会営業職を経て美容師の技術やデザイン、経営に特化した業界誌を発行する出版社K書房に勤務。総合誌・月刊B●B、書籍編集部経て会員制マネジメント誌編集部に異動。現在同部デスク。宝塚やジャニーズなどの「各種オタク」であることを認知されすぎて『ビジネスオタクではないか』と疑われるが、タカラヅカ受験経験アリ、上記ゼミ在学中の研究テーマは『シェイクスピアと宝塚/歌舞伎という上演装置』という筋金入り。趣味は、電車の中などで会った人のヘアスタイルを見てカット手順を脳内シュミレーションすること。宝塚鑑賞においてもヘアメイク技術はめっちゃ見る。ヅカから髪、盛大に公私混同が信条。
ブログ 『ヅカと、髪。』