木村信司 Mr.moonlight
2020.10.01
前回記事の結びの前に、私はこんなことを言った。
“ 浮世を離れた彼女たちに、いかに多くの【人生】を用意するか。
あの劇団の座付作家たちは多かれ少なかれそこに心を砕いている。”
谷正純さんが「比類ないバリエーション」でそれを叶えている一方、より近くで、まるで伴走するかのうように向き合っていると感じるのが、今回紹介する木村信司先生である。
木村さんの話に入る前に、自分が本職(美容師さん向けの専門書編集)で携わったムック制作の取材時に聞いた、象徴的な言葉を紹介したいと思う。
2019年4月28日に発売した『シブヤカラー』(髪書房刊)。渋谷駅周辺を美容の新しい“聖地“として、ヘアやカルチャーの多方面から特集したものだ。その中で幸福なことに、山下達郎さんやフリッパーズ・ギターのデビューに携わった音楽プロデューサー・牧村憲一さんにインタビューさせてもらったのだ。ここに再掲するのは、その中でもらった金言である。
「ある新人アーティストのCDを10万枚売らねばならないとします。その10万枚を一夜で売ってしまうのか、1年に1万枚、10年売れるCDにするのか。ビジネスとして正解なのは前者ですが、音楽プロデューサーとして目指すべきなのは後者なんです」
これは私自身の美容業界誌編集としての姿勢にも大きな影響を与えているし、このコラムで「木村信司さん」を取り扱うと決めた時に一番に頭に浮かんだ言葉であった。
渋谷音楽図鑑(柴那典・牧村憲一・藤井丈司/太田出版/2017年)
http://www.ohtabooks.com/publish/2017/07/04123250.html

そんな木村さんは1988年入団。普通、宝塚歌劇の座付作家はバウホール劇場という約500名収容の専用小劇場から経験を積むが、彼は1993年に『扉のこちら』(月組大劇場公演/主演 天海祐希・麻乃佳世)で演出家デビューを果たす。ちなみにこの作品は、今や宝塚ファンでなくても知らない人はいないであろう天海祐希さんが、入団7年目という異例の速さで主演就任したお披露目公演である。また、オー・ヘンリの『よみがえった改心(A Retrieved Reformation)』が原作になっている、軽快な金庫破りの話である。
そんなふうに、彼の作家人生は“彗星のように現れたトップオブトップスター“とともに、扉を破るように幕を開けた。
私が宝塚を見始めたのはもっと後のことで、さらに地方在住で映像と現地が行ったり来たりするものだから、初めて触れたのは『ゼンダ城の虜』(2000年 月組大劇場公演/主演 真琴つばさ・檀れい)だったと思う。その後、順番が前後して『十二夜』(1999年 月組宝塚バウホール公演/主演 大和悠河)を見たりした。
一般的に彼が“興行した“といえる作品は『鳳凰伝』(2002年 宙組宝塚大劇場公演/主演 和央ようか・花總まり)、『王家に捧ぐ歌』(2003年 星組宝塚大劇場公演/主演 湖月わたる・安蘭けい・檀れい)のオペラ原作2作だろう。『鳳凰伝』は、かつて冬季オリンピックのフィギュアスケート金メダリスト・荒川静香さんが競技に楽曲を用いたことで話題になった『トゥーランドット』が原作である。また、『王家に捧ぐ歌』は、有名なオペラ『アイーダ』がモチーフになっている。
そんなふうに並べてみると、字面からは古典的なタイプの作家に見えるかと思うが……
ハッキリ言ってロックンローラー。ファンの中でも「好き嫌い」がしっかり分かれる作風、それが木村信司さんという作家の1つの特徴だ。
特に、その作風が「お嫌いだ」とおっしゃる方の主張は2点ある。代表的な理由は「意味を持たない歌詞」と「役が少ない」、この2つである。
「役が少ない」という批判は、宝塚はスターシステムであること、前々回 柴田侑宏さんの回で紹介した“パトロン=タニマチ型“を参照の上、類推してほしい。宝塚ファンの多くは、あくまで作品より応援するスターを見にきているために往々にして起こる、この界隈独特の批判である。
では、「意味を持たない歌詞」とはどういうことか。それは、先の『王家に捧ぐ歌』の上演時から20年弱物議を醸し、もはやヅカオタにとっての“スラング“になっている歌詞を紹介して説明しよう。
『王家に捧ぐ歌』は、エチオピアの王女アイーダが、敵国のエジプトに囚われながら、将軍ラダメスに対する恋と尊敬、父親との確執といった障壁と闘いながら、平和や尊厳を守り抜くいきざまを描いたオペラである。
その中で、将軍ラダメスに恋するエジプトの王女アムネリスの側近たち(取り巻きの女たち)がこんな歌を歌う。
「エジプトはツヨい エジプトはスゴイ
スゴスゴ ツヨツヨ
エジプトはスゴくてツヨい」
まあこれが、当時、非常に物議を醸した。「くだらない」だの「ふざけている、こんな歌詞を生徒さん(出演者)に歌わせるな」だの。
筆者は「PUFFYっぽくてカワイイやん(世代)」くらいにしか思わなかったが、「都市型ポップスに馴染みのない層=歌詞に意味を持たせたい層」にはかなり衝撃的だったらしい。この件以降、木村さんといえば「ああ、あの“スゴツヨ“の人」と言われるようになった。
長々とポジティブでない話で恐縮だが、木村さんの魅力を語るにおいて、この“スゴツヨ“問題を一旦論破しておく必要がどうしてもある。もうしばらくお付き合い願いたい。
「あの“スゴツヨ“」は、もはや言葉ではないというのが私の読解だ。
何かといえば、単なる雑音。
アイーダ目線でよくよく考えたならば、見知らぬ土地、言葉も文化もわからぬ取り巻き連中のイビリや自慢が、意味を持つ言語として捉えられるだろうか? 言葉がわからない未開の地域で、現地の人にただ罵られているところを想像してほしい。
さらに、言葉が通じる側の人間であるアムネリスとしても、その取り巻きたちの「賛辞」は無味乾燥で空虚なものだった。本当に好きな人・ラダメスの言葉だけが欲しく、それだけが手に入らない。そんな彼女にとって、取り巻きの賛辞は言葉以下のものに聞こえるのではないか。
勇敢で美しいアイーダと出会って自らの使命と正義について葛藤し始める将軍ラダメスにとっても同じことである。
群衆の煽りに意味を持たせないことで、ただの冷たい刃物に見せているのだと思う。
その言葉たちが、アイーダやエチオピアの人々の誇りを滅多刺しにし、ラダメスの首に突きつけられ、アムネリスの手にその血を塗り付ける。
事実、その取り巻きの女たちと対比される、核となる2人の女性、アイーダとアムネリスが発する言葉は、誰の言葉よりも重い意味が与えられている。
アイーダ ひとつだけ、できることがあるわ。祈ることよ。この世界、愛し合う者たちが死ななくて済むように。
アムネリス いつか人々は戦い始めるでしょう。そして、戦いはいつまでも続くでしょう。しかし、たとえ戦おうと、戦いで傷つこうと、我々は決して平和への希望を失ってはならないのです。
このことから木村さんの作風は、これまで紹介した柴田さんのリアルな群像劇、谷さんの泥臭いスペクタクルと一線を画し、主演以外が完全に“装置“となっていることがよくわかる。そのことによって、敵対する国に生まれた2人の才能あふれる女性が、実は同じ信念の元に生きていた……。それが宝塚翻案版タイトルでいう“王家に捧げられる“歌とは、2人の女性のみずみずしい言葉だったということがわかる寸法だ。
この「言葉を奪う」ことで人物が虚無・装置化するパターンは非常に多く『スサノオ』(2004年/雪組宝塚大劇場/主演 朝海ひかる・舞風りら)、『暁のローマ』(2006年/月組宝塚大劇場公演/主演 轟悠・瀬奈じゅん)などが挙げられる。
ついでに言うと、こうやって主演周り以外が「装置化」するので、役が少なくなるわけである。この2つの批判は深くつながっていて、なおかつ“木村オペラ“の本質そのもののように感じている。
逆説的に言うと、木村さんの作品で「言葉を与えられる」というのはスペシャルなことなのだ。

「嫌い派」への回収にスペースを取り過ぎてしまったが、木村さんの魅力は、この「装置」というキーワードにある。物語を再現する装置、つまりインスタレーションの読解の深さが他の演出家に類を見ない。
私が彼の作品で最も好きな作品は、先にも紹介した『スサノオ』(2004年雪組)である。
この年は、遡ること1998年に新しく宙組が新設された際から引きずっている“スターシステム“の歪みに加え、各組のトップに準ずるスター男役(二番手と呼ばれる)が本来属する組と違う組に特別出演するという催事も執り行われており、ハッキリ言って大混乱だった。
(ヅカオタは2004年を地獄のシャッフルイヤーと呼ぶ)
ファンでない人にわかりやすく、あえて乱暴に説明すると、これまでのピラミッドが崩壊し、それ以前のルールなら順当にトップスターを目指せていそうな人が「専科」という“脇役スペシャリスト“に置かれ、スターダムの外にいた人材がスター路線に躍り出てきた番狂わせが起こった。それに加えての「二番手シャッフル」なので、ファンは一喜一憂・右往左往した。
そんな年の春、4月頃に上演された同作品。日本の成り立ちに関わる「八岐大蛇」と「天岩戸神話」が下敷きになった作品だった。
粗暴で若き血滾る皇子スサノオノミコトを若い「躍り出てきた立場」のトップスターの朝海ひかる、そのスサノオを誘惑し、妖艶なカリスマ性を持つ敵アオセトナを他組から「シャッフル特別出演枠」の水夏希、そして世界を照らすアマテラスを先述2人よりもベテランで実力のある「専科」の初風緑が演じた。この字面だけでも、随分と入念な“当て書き“であることがわかる。宝塚の座付作家の強みは、この“当て書き“が叶うことにある。
*当て書き---演劇や映画などで、その役を演じる俳優をあらかじめ決めておいてから脚本を書くこと。
――ここから後日談だが、この「スサノオ」が任期を終えて卒業したのち、「アオセトナ」がこの雪組に人事異動してきて主演男役の後任に、「アマテラス」はトップスターにならぬまま卒業を決めることになる。
当て書きが叶うことは、残酷でもある。
私が最もこの作品で美しいと思ったのは、ラストシーンである。
一度死んで復活する、スサノオ。その時のスサノオは真っ赤な衣装を着て白い民衆(装置)の真ん中に立つ。それを見て、多少なりとも想像力がある観客は「あの赤は闘いの末の“血“であり、アマテラスの“日“なんだな」と読む。
真っ赤な衣装をまとった朝海(スサノオ)を中心に、舞台に日の丸が作られる。
私はそれを見てトップスターというのは彼女に限らず、他の出演者やファンにとっての“太陽“であって、一方たくさんのライバルの“卒業(屍)“を乗り越えてあそこに立つんだなとめちゃくちゃ痛感した。
自分が宝塚受験のためのレッスンを受けていた時だからこそそう思ったし、今もなお見返すたびにあの“日の丸“がズンッと心臓にくる。
主演以外を装置としている以上に、あの「宝塚」というインスタレーションに、濃すぎるくらいに人(生徒)の生き様や闘いを投影して一緒に成仏させようと願うのが木村信司作品の真骨頂だろうか。
当て書きが叶うことは残酷で、だから美しい。

宝塚のスターシステムそのものは非常に残酷で、アイドル以上に「センターとその他」をはっきり分けるものだ。木村さんの作品への形容を再度用いるなら「言葉を持つ人と装置」というくらいの違いと言ってもいいほどの溝が横たわる。
そんな中で彼の当て書きが残酷で、かつ美しいのは、冒頭で紹介した「天海祐希との船出」に発端があるんじゃないかなと、傍目に感じている。抜擢されるスターは若ければ若いほど、仲間やファンにその気がなくても、本人にとってはまるで針の筵に立つようだという。天海さんといえば今や押しも押されもせぬ地位を確立したが、彼女が刺すような視線を一身に受けて走り抜けたのを一番近くで見ていた彼が、「センターとその他」「人と装置」を描こうとする時、「言葉を持つ側の痛み」を表現したくなるのは非常にうなずけることだ。
“地獄のシャッフルイヤー“の説明でも触れたが、宝塚のスターシステムが残酷であることはファンにとってはわかりきった大前提でありながら、それによって、ファンは傍目から見たら「親戚か何かですか?」というくらい一喜一憂する。応援している「贔屓(推し)」がスターの座に届かなければ一緒に悲しみ、なったらなったで同じように針の筵に立たされるのが宝塚ファンである。非常に忙しくややこしい存在なので、彼女たちの「痛み」を“昇華“してくれる作品に出会うと、涙を流して成仏する傾向がある。
木村さんの作品は、前回・前々回の2人や昨今の本格ミュージカル系の作品に比べて大ヒットはさほど多くない。ただ、その分木村さんが携わった作品の主要な役回りを演じたスターのファンには「あの作品が転機」「よりどころ」という人が多い。
つまり、その思い入れが“成仏させた“スターの数だけ分散するから、爆発的な興行がない。
正に「1万枚を10年売り続ける」そんな人なのである。
最後に、彼の副題を「Mr.moonlight」とした意味だけ明かして結びたい。
1つは、彼が宝塚歌劇の専門チャンネル内で
「僕、デビュー後月組(の公演担当)ばっかり続いたんだよね〜」
「月組が合ってると思われていたみたい」
と言っていたこと。
天海祐希さんも月組の元トップスターだが、これを聞いて「ああ、そうかも」と思った。
月組って、いつも体制と逆行し「生みの痛み」と闘っている攻めの組だなあという印象があったからなのだ。
スターシステムだけで見るなら、天海祐希さんに限らず、大地真央・黒木瞳コンビも超若手の大抜擢。黒木瞳さんに至ってはキャリア1年とちょっとでの主演就任だった。現在トップスターの珠城りょうさんも入団9年目でのトップ就任で「天海祐希に次ぐ抜擢」と報道され、大きな体を震わせながら恐縮していたのが記憶に新しい。
これは別に、番狂わせや話題性のために本人たちを不当に「痛めている」のではないし、ましてや組ごとの管理能力の偏差によるものではないと私は考えている。
1921年に公演数や生徒の増加に伴い、花組と分かれる形で生まれた2番目の組は、いつしか新しいことをやるのが役割になった。
1967年、宝塚初のブロードウェイ作品となった『オクラホマ!』も月組上演。(星組と合同公演)
そしてかの有名な『ベルサイユのばら』(1974年)も月組が初演。今や宝塚の代名詞になった「ベルばら」だが、当初「少女漫画などを宝塚でやるなんて」と紛糾したという。
続いて1977年『風と共に去りぬ』初演で「男役スターが口髭をつける」という今や当たり前となった文化の“初めて“も月組スターが開拓していった。
そんな、茨を振り払いながら前に進んできた月組が木村さんを育て、その木村さんがたくさんのスターとファンの「痛み」を成仏させているんだな〜と思い、彼をスターを照らす月光に例えたくなった次第である。
そしてもう1つ。
これは個人的な思い出なのだが、私たち世代にとって「Mr.moonlight」といえば、モーニング娘。さんの2001年13枚目のシングルである。元々「宝塚を意識して作られた」という当曲だが、問題はそこではなくて、当時新加入したばかりの高橋愛さん初の参加曲である。
高橋愛さん自身も宝塚ファンであることで知られているが、ぜひ動画などで楽曲を披露している映像を見てほしい。はっきり言って役回りは「装置」なのだが、目を引く「装置」としてのパフォーマンスぶりが圧巻なのだ。
なんというみずみずしい「モブ」の演技……!
そうしているうちに、月日は流れ、元々メインボーカルを務めていた後藤真希さんら3名の卒業後は、リーダーとなった彼女が1人でメインボーカルを務める。「装置が言葉を得る」ストーリーまで宝塚らしい楽曲なのだ。
木村さんの作品を「役が少ない」とご不満の宝塚ファンに、ぜひ見てほしい装置としてのベストパフォーマンスとストーリー……。
そんな皮肉がこもっていることも、無粋ながら自ら付け加えておきたい。
スポットライトの当たらないところでのどんな努力も、みんな見ている。それが宝塚の座付作家だし、私たちファンもそうでしょう?と。
お日様が直接当たらないところにいるのなら、私たちが視線で光を当てられること。
そして、言葉が冷たい刃物になること。
それが宝塚の醍醐味であり、危うさでもあるということを、太陽ほどの大きなパワーはないけれども、絶えずあたたかい光を当て続けて教えてくれているように感じている。


























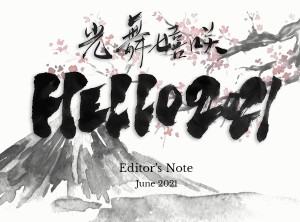


ななしましゅうこ/1986年生まれ、福岡県出身。立命館大学文学部学際プログラム(現・文化芸術専攻)卒業。某放送協会営業職を経て美容師の技術やデザイン、経営に特化した業界誌を発行する出版社K書房に勤務。総合誌・月刊B●B、書籍編集部経て会員制マネジメント誌編集部に異動。現在同部デスク。宝塚やジャニーズなどの「各種オタク」であることを認知されすぎて『ビジネスオタクではないか』と疑われるが、タカラヅカ受験経験アリ、上記ゼミ在学中の研究テーマは『シェイクスピアと宝塚/歌舞伎という上演装置』という筋金入り。趣味は、電車の中などで会った人のヘアスタイルを見てカット手順を脳内シュミレーションすること。宝塚鑑賞においてもヘアメイク技術はめっちゃ見る。ヅカから髪、盛大に公私混同が信条。
ブログ 『ヅカと、髪。』