上田久美子 噺家
2020.12.02
私の現在所属する会社は、美容室向けの業界誌を編集・発行している会社である。
こうやってアートや文学が好きで美容専門誌編集をしているというと、美容の技術やセンスに詳しいと思われがちだが、何がどうして私は小社勤続のうち、半分を経営誌編集として過ごした。
美容室経営者とはギルド的稼業とトレンドビジネス的企業の間で揺れ動き、真っ当な美容人であれば引き裂かれるような葛藤していると思う。ビジネスと技の継承と。そんなことは両立できるのだろうか・・・。
そんな小社業務の中で知った経営者の視点というものがある。
・鳥の目 俯瞰して全体をとらえる見方
・虫の目 組織の隅々まで細部をとらえる見方
・魚の目 時流を読み、変化をとらえる見方
これまでの記事で紹介した作家のうち、自身の型をぶっ壊しながら進化していく谷正純さんは「魚の目」、スター一人ひとりの流れる血1滴まで書き留める木村信司さんは「虫の目」をもって宝塚歌劇団を見ていると思う。
今回紹介する上田久美子さんは、まるで「鳥の目」――クールなヒットメーカーだ。
2006年に入団。2013年に『月雲の皇子 -衣通姫伝説より-』(宝塚バウホール公演/主演 珠城りょう・鳳月杏・咲妃みゆ)にてデビュー。これが興行・評判ともに好評を博し、異例の年内再演を果たす(天王洲銀河劇場公演/出演者同)。それだけでなく、ある出演者が出演番組内でこう言及したことが、上田さんの“逸材ぶり“の証拠と言えそうだ。
夏美よう 久しぶりにすごい作品だったから。稽古場の空気が違った
(『マイスターの教え』宝塚歌劇専門チャンネル・タカラヅカ・スカイ・ステージより)
この夏美ようさんとは、宝塚歌劇団の出演者の中で花・月・雪・星・宙の「5組」に現在属していない「専科」所属の出演者である。専科所属の多くは前述の「組」に配属した経験も踏まえ、芝居・歌・舞踊・ビジュアルメイクなど卓越した得意ジャンルを持つ、いわゆる“燻し銀“たちが顔を揃えており、各組の興行に特別出演する形で縁の下から支える存在だ。
その夏美さんは1976年入団の大ベテラン。星組の組長(単語レベルだと物騒な呼び方だが、その組の最上級生の役職、いわゆる管理職である)を務めたこともある人だ。かたや上田さんは2006年入団で、年次だけで30年の開きがある。
その30年の開きをもってして「久しぶりにすごい」と言わしめたのは、単に情緒とかセンスだけではないと、私は考えている。
この発言を放送で見た時、まず改めて宝塚歌劇の座付作家というのは、シビアな世界に生きているのだなと思った。30年先輩を「使う」仕事なのだ。
その大ベテランたる夏美さんが、わざわざ公共の場で質の高さに言及するとはどういうことか。自分も一端の専門誌編集の仕事の中で、ベテラン美容師の先生に怒られたり褒められたりしていただきながら働いている分、尚更感じるものがあった。
また、あえて普段「取り立てて言及せずに」粛々と舞台に立たれている意味、懐の深さと愛情も感じて、背筋に走るものがあるわけである。
上田久美子さんは、優秀な“作家“というよりーーそれが、今回のテーマである。

兎にも角にも「宝塚歌劇団演出家・上田久美子」は優秀な作家である。
先述の鮮烈な公演の翌年、『翼ある人びと−ブラームスとクララ・シューマン−』(2014年 宙組シアター・ドラマシティ公演/主演 朝夏まなと・緒月遠麻・伶美うらら)が第18回鶴屋南北戯曲賞候補にノミネート。さらに翌年『星逢一夜』(2015年 雪組宝塚大劇場公演/主演 早霧せいな・咲妃みゆ・望海風斗)で第23回読売演劇大賞・優秀演出家賞を受賞する。
だから、わざわざ私がこんな駄文で“推さなければいけない“ほど日頃軽んじられている存在の「座付作家」である割に、安定したファンが多い。これが大きな特徴だ。
まず、背景から説明すると、宝塚ファンは権威に弱い。連載初回で言ったように「存在はメジャーなのに実態がニッチ」だからか、一般的な評価や権威のある賞や、外の目が大層気になるようだ。「夫も面白いって言ってる」に始まり、「この作品(出演者)なら外部公演でも遜色ない!」といったような具合に。
前回結びに紹介したブロードウェイミュージカル『オクラホマ!』(1967年月組初演)は、その“認められたい塊“であり、それが大衆化への原動力であったからそのことを否定するつもりは毛頭なく、ただ「そういうところがある」という視点を紹介したに過ぎない。
“ニッチ“から脱却したいということなんだろう。
この権威主義は宝塚システムの本質的性質で、多かれ少なかれ逃れられないものだ。
繰り返し言及している「トップスター中心のスターシステム」が、パターナリズムそのものだからである。先程夏美さんを「組長」と紹介したが、トップスターを中心としたスター路線のピラミッドに加えて、夏美さんが務めた組長から連なる「徹底した年功序列・成績順」の序列という2つの階級制度が存在し、その二重の序列のシステムが染み付いたカルチャーなのである。
最近某新聞社が論じたような、そのことが良いか悪いかは放っておいていただいて、そういった厳しい序列社会をもってあの一糸乱れぬパフォーマンスが叶えられており、我々ファン側もそれを理解して応援するという“作法“なのである。
結論は簡単で、そんなパターナリズムに洗脳されたファン目線でいえば「彗星の如く“外部賞=権威“をかっさらいまくる“女性演出家“」というのは、スターさながらの存在感に映ったに違いない。
2つ目は「失敗がない」ということだ。先の鮮烈なデビュー公演から宝塚大劇場公演『星逢一夜』まで、前回の木村さん・前々回の谷さんの記事で紹介したような「!?」が飛ぶ作品がないのだ。
個人的には、これはSNS社会のイヤな傾向だと思うが「失敗もあるがユニークな作家」より、「私、失敗しないんで」を好むという現代性の象徴のようにも感じている。
そんなわけで、座付作家・上田久美子に厚い信頼を寄せるヅカオタは多い。
ダメ押しの京都大学文学部卒という“権威“までお持ちで、もう無双だと思う。それが理由で彼女を推してるわけじゃない!というファンは多いだろうだが、「それと逆の理由で他の座付作家を気軽に酷評してみせる」観客が一定数いるという事実も、悲しいかな記しておきたい。

「いやいや、この連載ってさ、“推したい座付“を紹介するんと違うん?」
という声が聞こえてくるようだ。まあ待ってください……、じきに種明かしをします。ちゃんと好きな作品もあるので。
ただ、作品そのものよりもその出し方、“戦略“にまずうならされる。こちらをまだ、私の「好き」より先に紹介しておきたい。
彼女が作る作品は【精巧な宝塚型】のヴァリエーションなのである。
それは、作品構成。
私は今回、作品データを引用する際、前回までの記事と違う書き方をした。
(主演 男役の主役・男役の準主役・ヒロイン)という書き方だ。
※『星逢一夜』のみ作品特性を鑑みヒロインを先に記述
これを私は【あかねさす型】と呼んでいる。1人のヒロインをめぐる主役(ヒーロー)と準主役(ヒール)の物語だ。
なぜ【あかねさす型】かといえば、連載2回でも紹介した『あかねさす紫の花』(初演 1976年花組宝塚大劇場公演/主演 榛名由梨・安奈淳・上原まり)に則っている。2人の皇子が1人の才能豊かな美しい皇女をめぐって恋の火花を散らしたというロマンスである。
デビュー作から追っていこう。
『月雲の皇子』は“衣通姫伝説“をモチーフにした木梨軽皇子と弟皇子・穴穂皇子による「妹」の衣通をめぐる恋と権力の攻防である。
『翼ある人びと』は、伝説のスキャンダル、ブラームスとクララ・シューマン(シューマン夫人)、そしてブラームスの師シューマン、3人の恋を超えた愛、畏敬の物語。
『星逢一夜』も、時は江戸時代、架空の藩の藩主の嫡男・晴興が、幼なじみである里の娘・泉と、同じく幼なじみで彼女に想いを寄せる源太との愛と友情の……。
もうね、そういうことです。「絶対宝塚ファンが好きな1つの“型“」をしつこく展開していくことで、確実に信頼を摑んだという経緯だと踏んでいる。
ただ、この後の『金色の砂漠』(2016年花組 宝塚大劇場公演/主演 明日海りお・花乃まりあ)と『神々の土地』(2017年宙組 宝塚大劇場公演/主演 朝夏まなと・真風涼帆)はトントーンと、むしろめちゃくちゃ異色のテイストをやってのける。
ここがうまいところで、だから一瞬その“型感“が「気のせいだったかな?」となるのね。
その後、2019年。『霧深きエルベのほとり』(星組宝塚大劇場公演/主演 紅ゆずる・綺咲愛里・礼真琴)の潤色を手掛けたことで、気のせいではないと確信に変わることになった。
これは、日本演劇界の草分けであり、宝塚歌劇にも多数名作を残す菊田一夫氏が遺した作品で、1963年・1967年・1973年・1983年と何度も再演されている作品だ。これが2019年の正月公演に「Once upon a time in TAKARAZUKA」とサブタイトルを銘打って発表されたものだった。細かい経緯は省略するが、宝塚の歴史において「過去の巨匠の遺作」を潤色する作家の中で、1番キャリアが短く、さらに女性作家は初めてなのじゃないかと思う。
このプログラム中、彼女はこんなことを書いている。宝塚の入団試験を受けようと情報収集をしていたときのことだそう。
「古めかしい作品だろうと予想して読み始めた脚本が、シンプルで完璧な物語構造を持ち、素朴なセリフの中に本物の男らしさを宿した、たいへん上質な戯曲であることに、今も忘れられない衝撃を受けました」(東京宝塚劇場公演 公演プログラムより)
私はその挨拶を読んで「この人はあえてこの物語構造を後世に語り継ぐつもりなのだな」と察したのである。
この作品は、無骨な船乗りカール・シュナイダーと地元の令嬢マルギットの泡沫の恋、その婚約者フロリアンを巻き込み、お互いを思い合う人情が描かれた三角の物語構造だった。
この「三角」のヴァリエーションこそ、宝塚の方程式だという強い宣言に見えた。
事実、宝塚のトップスターを中心としたスターシステムの両脇をヒロインと準主役が支えるという構図は近年強固な“パッケージ“となりつつある。
恋を中心に、権力争いや、友情。これが宝塚ファンの特性以前に、「システムに安心する」時代の思考停止した現代人に怖いほどフィットしている。だから今宝塚ファンの多くが上田久美子に心の臓を摑まれている。そんな状況だ。
それは一見怖くて浅薄なことだが、私は非常に好意的に受け取っている。

1つは、彼女自身は実は、そんな思考停止社会を疑問視していると思うからだ。
彼女の真骨頂は先ほど「トントーンと、むしろ異色のテイスト」と紹介した『金色の砂漠』『神々の土地』、さらに『BADDY』(2018年 月組宝塚大劇場公演/主演 珠城りょう・愛希れいか・美弥るりか)がある。一見楽しい現代的なコミックショーなのだが、この作品の主題は明らかに“型“の破壊であった。
これは、タカラヅカ基礎知識的には、この連載で取り扱ってきた「芝居(物語中心の出し物)」ではなく「ショー(音楽や舞踊などパフォーマンス中心の出し物)」になる。が、もはや、そんな「ショーとはこうだ」みたいな薄っぺらい分類を寄せ付けない強い思想とエネルギーが『BADDY』にはあった。
この作品の主人公は、治安の良い平和な地球から追われた“ワル“バッディ(珠城)。パートナーのスイートハート(美弥)やワルの仲間たちと、月(流刑地)から地球に侵略してくるシーンから幕が開く。
この“平和な地球“を守るのは、穢れを知らず正義感あふれる女性捜査官グッディ(愛希)。襲来した“悪“から地球を守ろうとするのだが、次第にバッディが巻き起こす事件から、周りの人間たちの感情の動きに自分も心掻き乱されていき……。
と、いうストーリーだ。オチを言っちゃうと、バッディとグッディはお互いに惹かれあい、スイートハートはそんな「矮小になっていく」バッディに愛想を尽かし、バッディにグッディは銃口を向け……という話。一応補記しておくとスイートハート役の美弥るりかさんは「二番手男役スター」だった。とはいえ、男性ギャングに扮するシーン以外に、ユニセックスな装い、セクシーなスリット入りの完全に女性役のドレスルックなど変幻自在な存在なので、この補足すら上田さん的には“無粋“なのだと思う。
これは鮮烈だった。宝塚のいろんなシステムや慣例、自分が武器にしているはずの“物語構造“さえもパロディ化した描きっぷり。さらに現代に生きる私たちの価値観をもグーでぶん殴るような……。今なお根強い「中毒者」の多い作品となった。
2つ目。
上田さんは、この、おそらく自分の「本音」に近い部分を【ごくたまに戦略的に】【信頼している主演とのタッグで慎重に出してくる】ところがある。これが私は「編集=人の才能を使う職業」としても、痺れて好きな次第なのである。
戦略的なところを再説明しておくと、3回は“顧客の好きな型“を繰り返す。
そこから、破壊する。破壊して、直す。また破壊。そのリズムが、非常にうまい。
信頼している主演のタッグというのは、先述の『神々の土地』は、大好評を博した『翼ある人々』のブラームス役・朝夏まなとさんに。これは朝夏さんの退団公演だった。
さらに『BADDY』のバッディ役は、鮮烈すぎるデビュー作『月雲の皇子』の木梨軽皇子をわずか6年目というキャリアで務め、客席を満席に埋めて東上を叶えてくれた珠城りょうさんだった。
私は、上田さんの戦略と情緒のバランスがたまらなく好きなのである。
単に自分のやりたいことだけを貫く作家もいるし、逆に戦略に身を売る作家もいる。ただ、難しいのは、私はそれをどちらもいいとも思っているのだが。
彼女が見ている「戦略」は何なんだろう……。
その答えは、宝塚歌劇専門チャンネル・タカラヅカ・スカイ・ステージ内の番組『演出家プリズム #3』内にあった。京都大学時代の学友・愛知県美術館学芸員の中村史子さんをゲストに招き、お互いのビジョンを語っていた。
上田(宝塚歌劇に出会って)大変ユニークな文化だと思った。これを保存すること。
この放送そのものは2013年だったようだが、すべてが繋がったような気がした。
この人のビジョンは文化の保存で、クリエイティビティにはゴールがないのだ。だから、まずは自分が、次に宝塚そのものが明日もあり続けることを優先するのだと理解したのである。
同じ“人を使う“仕事である編集目線で見ても「まずは自分が」というのはめちゃちゃ大事だと思う。
まずは私が何かの信用を得ないことには、誰もこちらの「保存しましょう!」を聞いてはくれないだろう。
他の座付作家ほどではないけども、彼女も例に漏れず「宝塚らしくない」とか「宝塚ってこんなもんでしょと思っている」というような批判にさらされるケースも目にしたことがある。
その2つを丁寧に論破するなら、まず型という明快な解で「らしさ」は研究し尽くしている。たまにSFやら架空の奴隷制度やら、テーマが突飛なものもあることは確かだが、物語構成に加えて、連載2回で言及した「柴田流の余韻の美学=最後の一文」も毎回秀逸だ。宝塚ファンのツボは、よく研究されていると思う。
それが逆に「宝塚ってこんなもんでしょ」感につながっているのかもしれない。ただ、これは論破ではないのだけど、大変申し訳ないが、私も「宝塚ってこんなもん」だと思うのだ。
だから私も「文学“入門“」と言っている。
限られた条件の中で最大公約数の宝塚ファンが喜ぶものを作ろうと思えば、上田さんがデビュー3作で開発した“型“にしか答えはない。
前回までの谷さん・木村さんと大きく違うのはここだ。
彼女は「鳥の目」で、この文化そのものを守ろうとしている。明日にこの仕組みを遺すこと。だから最大公約数に受けなければいけない。その貴重な仕組みを、ニッチに守ったままで。
Once upon a time, long long ago, there is a pretty girl…
この人は作家というより噺家なのだと思うわけである。
「むかし、乙女がおりました」
から、始まる物語。恋、権力、友情と、毎回少し粋なオチをつけて……。新作を書き、たまには古典を話してみせる人。
宝塚歌劇というニッチな扉の先では、出演者だけでなく私たち観客もおとぎ話を聞く少女に戻るのかもしれない。上田作品に触れるたびに、このカルチャーの本質を省みる。
違いは、ただ一つ。その結びが「おしまい」じゃないことだ。
上田さんは必ずまた幕を開けてくれ、いっぱいの観客を沸かせるんだろう。観客と、出演者側からの、そんな期待を一身に背負って紡ぎ続ける気鋭の語り部だ。
Tomorrow again!
戦略と情緒の噺家に、お客の私は今日も緞帳のこちらから「また会えますように」と心を贈る。
大切だから、なくならないでと。
事業が、カルチャーが継がれていく根っこって、多分こういうことだ。


























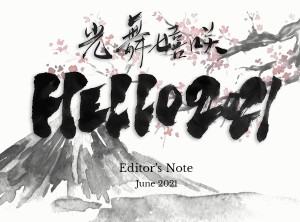


ななしましゅうこ/1986年生まれ、福岡県出身。立命館大学文学部学際プログラム(現・文化芸術専攻)卒業。某放送協会営業職を経て美容師の技術やデザイン、経営に特化した業界誌を発行する出版社K書房に勤務。総合誌・月刊B●B、書籍編集部経て会員制マネジメント誌編集部に異動。現在同部デスク。宝塚やジャニーズなどの「各種オタク」であることを認知されすぎて『ビジネスオタクではないか』と疑われるが、タカラヅカ受験経験アリ、上記ゼミ在学中の研究テーマは『シェイクスピアと宝塚/歌舞伎という上演装置』という筋金入り。趣味は、電車の中などで会った人のヘアスタイルを見てカット手順を脳内シュミレーションすること。宝塚鑑賞においてもヘアメイク技術はめっちゃ見る。ヅカから髪、盛大に公私混同が信条。
ブログ 『ヅカと、髪。』