小柳奈穂子 白馬
2021.01.12
こういったウェブ記事に限らず雑誌でも新聞でも、多くの場合連載を企画するときは開始前に全体の構成を考える。
この連載の場合は宝塚歌劇の「座付作家」をテーマにしているので、すなわち決められた回数分「推したい座付作家」をピックアップしていく作業になる。
それはもちろん基本的には好きな作家さんであって、ほぼ決め打ちで、これでいくぞと思っていた。
だが、最近私ごとながら、本職(専門誌編集)でも紙媒体からウェブ媒体への転換をしていく中で、圧倒的なウェブの強みを実感することがある。
それは、時流対応だ。
小社の月刊誌は比較的時流のキャッチアップは早い方ながら(進行がギリギリともいう)(ごめんね各位)、ウェブのそれには敵わない。
そんなわけで、今回「ウェブ連載である強み」を活かして、当初考えた構成にねじ込んででも語りたい座付作家がいる。
それは、小柳奈穂子さんだ。
彼女と彼女の作品に心震わす私たち観客のために、どうしても今のこさねばならないこと。
小柳奈穂子さんは、1998年入団。『SLAPSTICK』(2002年/月組宝塚バウホール公演/主演 霧矢大夢・紫城るい)で演出家デビューを果たす。この作品は自分は拝見しておらず、彼女との個人的邂逅はどうやら『NAKED CITY』(2004年/花組宝塚バウホール公演/主演 彩吹真央・遠野あすか)だったようだ。
「だったようだ」というのには2つ理由がある。1つは、個人的にこの作品を拝見したのはヒロインである遠野あすかさんのファンだったからなのだが、作品そのものの印象については正直言って強く残っていない。残っていないということは、印象は悪くもなかったのだということはフォローしておきたい。
もう1つは、この作品の持ち味があまりにも今の小柳さんの芸風と違いすぎて、正直今この瞬間まで小柳さんの作品だと忘れていたということである。
では、小柳さんの“今の芸風”とは何か。
それは、宝塚における2.5次元的ミュージカル担当というオリジナリティである。
まず「2.5次元」とは何かというと、漫画やアニメ、ゲームなどの「2次元作品」を原作とする舞台の総称のことだ。俳優が演じる舞台は「3次元」であることから、2次元と3次元の間で「2.5」というらしい。2.5次元舞台は日本ミュージカルのお家芸となりつつあり、一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会なるものが存在し、毎年さまざまな作品が生まれ、さらにそれが中国や韓国など世界各国で上演され評価を得ているのである。
一般的に「テニミュ」と呼ばれる『テニスの王子様』のミュージカル版が知られているかと思うが、少年ジャンプやアニメでお馴染みの『NARUTO』(岸本斉史原作)や「ぼくの孫悟空」(手塚治虫作)を原作にした『GOKU』などは筆者のオススメで、秀逸なミュージカル作品である。ちなみに、この両作品の脚本・演出を手がける児玉明子氏は、元宝塚歌劇団の座付作家であったという裏話もある。
多くの人が「宝塚といえばベルばら」と池田理代子氏原作の少女漫画『ベルサイユのばら』を想起すると思うので、「宝塚で漫画原作なんて普通なんじゃないの」と思うかもしれないが、実はどうしてそうではないのですぞ……というのが、今回の主題の前提である。
私個人としては、少女漫画のキャラクターシステムと、宝塚のスターシステムは実は水と油だという見解を持っている。

さて、彼女のキャリアを遡れば、実は2003年にすでに「2.5次元」を手がけていた。『アメリカン・パイ』(2003年/雪組宝塚バウホール公演/主演 貴城けい・山科愛)で、これは萩尾望都氏の同名漫画が原作となっている。萩尾望都氏といえば、2018年に『ポーの一族』が小池修一郎氏の手によって宝塚大劇場で舞台化されたが、その15年前にすでに彼女は萩尾氏の世界観を宝塚に持ち込んでいたことになる。
さらに、先に「2.5次元ミュージカル」ではなく、「2.5次元“的“ミュージカル」と表現した理由も回収したい。
それは、漫画原作でない作品にも2.5次元=漫画原作のようなテイストの作品が多いということだ。その例としては『めぐり会いは再び』(2011年/星組宝塚大劇場公演/主演 柚希礼音・夢咲ねね)、『アリスの恋人』(2011年/月組バウホール公演/主演 明日海りお・愛希れいか)などがある。それぞれ、前者はフランスの劇作家マリヴォーの名作喜劇「愛と偶然との戯れ」、後者は知らない人はいないであろうルイス・キャロルの児童文学「不思議の国のアリス」といった古典を原作にしているのだが、それぞれ登場人物のキャラクターデザインが内面も外面もどちらも「2.5ナイズ」されているなという感想を持った。
まず、わかりやすい外面から述べると、男性キャラクターはみんな躍動感のある束感を強調したレイヤースタイルである。女性キャラクターはブロンドを通り越したホワイトブリーチで、いかにもお人形のようなマットな質感の髪や肌。ファッションも全て特定の時代考証を伴わない「どこか知らない遠い国」といった、ファンタジー要素たっぷりの雰囲気だ。
そして、内面。ここが最も個人的に注目すべき点だと思っているのだが、小柳さんが書く「2.5次元的」作品の主人公、特にヒロインは「等身大のがんばる女の子」なのである。
……今の直前の一文を「おお、確かに!」と思うのはおそらくかなり古(いにしえ)よりの宝塚ファンだけだと思う。一般的に、テレビドラマも映画も漫画も、女の子に限らず主人公が「等身大でがんばっていること」はごく当たり前だからだ。なぜなら、それが共感を呼びやすく、共感を呼ぶということは支持されるということだからである。
特に、少女漫画は「恋に友情に自分自身の成長に、等身大で悩んだり壁にぶつかったりしながらがんばる女の子」が主人公としてうってつけだ。「ガラスの仮面」やら「エースをねらえ!」に始まり、「花より男子」だって「NANA」だって、要はそういう話なわけであった。
ただ、宝塚歌劇は繰り返すように男役スターを中心としたガチガチのピラミッド型スターシステムで構成されてきた。と……すると 「等身大の女の子の成長譚」が、本来このスターシステムに実はフィットしないということが見えてこないだろうか。
男役トップスターが必ず主役で、対峙する相手役なりヒロインとして絶対的な存在感を示す娘役トップスターのカップル芸という縛りがある。さらに、その男役トップスターの傍にはヒール役やバディ役をこなす二番手男役がいる。
これ、勘のいい人はお分かりだろうが、宝塚のスターシステムの構造にフィットしているのは本当は少年漫画なのである。ナルトとサスケとサクラであり、花道と楓と晴子であり……!
娘役のトップはこれまで、少年漫画のヒロインよろしく「浅倉南的」であることが、実は暗黙の了解であった。
つまり、先に触れた『ベルサイユのばら』は少女漫画的には特殊であって、なぜなら主人公オスカルが「女性だけれどもなんやかんや事情があって男装をしている」というかなり特異な物語構造をしているのである。
つまり『ベルサイユのばら』によって、一見宝塚は「少女漫画的」なものを上演する装置にうってつけのように見えたが、その実本来は全く逆で、本当は少女漫画的なものを上演するには世界一向かない装置であるということをわかっておかねばならない。
(ビジュアルの再現性に関する適性を除く。)
では、その「世界一少女漫画を上演するには向かない装置」である宝塚歌劇で、小柳さんがどのようにして「2.5次元的ミュージカル」という持ち味を確立するに至ったか。
それは、彼女が誰よりも「人を読解する力」が長けていることが強い推進力になったと見ている。演者の内面をキャラクターに投影するのが上手いのだ。
例えば、先述の『NAKED CITY』。主演の彩吹真央さん自身がカメラを趣味にしていることから想起したキャラクター設定だという。
また、篠原千絵氏の少女漫画を原作にした『天は赤い河のほとり』(2018年/宙組宝塚大劇場公演/主演 真風涼帆・星風まどか)は、主演コンビの主演就任作品。男らしい魅力の真風さんに対し、高い技術力ながら童顔で経験不足の相手役星風さんを「真風の相手役には子供っぽい」と評する声もあった。そんな中、「タイムスリップしてきた高校生と異国異次元の王子」を当てる大胆ながらぴったりの当て書きで、むしろ星風さんでなければ真風さんの相手役はできないのだという世界観を作り上げ、二人を盛り上げてみせた。
『Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀』(2018年/星組台湾公演ほか/主演 紅ゆずる・綺咲愛里・七海ひろき)では、この折“美丈夫だらけ“だった星組のビジュアル系スターを余すことなく使い切り、海を渡った。この作品の原作は台湾の伝統的な布袋劇をベースにした日本と台湾の合作によるSF人形劇で、人形を使い手が操って表情豊かな会話劇からアクロバティックな戦闘シーンまでを繰り広げることが持ち味だ。筆者はこの時分の星組ファンだったからあえていうが、主演コンビを中心とした当時の星組は「見た目は抜群にいいが歌や踊りの精度は今ひとつ、だがなぜか娘役の下級生に至るまで殺陣だけはやたら上手い」というのが長年の評価だったので、この作品をこの頃の星組に当てたのはうなるほかなかった。ちなみに、この作品で原作での事実上の主役・殤不患を演じた七海ひろきさんは、元々筋金入りのアニメ・漫画ファンで、持ち前の美しさと熱意が高じて宝塚退団後2.5次元舞台のNo.1人気演目と言っても過言ではない『刀剣乱舞』シリーズに出演した経緯がある。
美丈夫であることはそれだけで俳優として価値がある、今の星組の良さは“浄瑠璃的な“ところなのだと、紅・綺咲・七海のファンは背骨が折れるほどに背中を押してもらえた気がしたものである。
そんなふうに彼女らしい作品が次々に生まれつつ、その作品はどこか、宝塚の中で特異であるような雰囲気も拭えずにいた。
彼女のポジティブさや「等身大」の優しさで、宝塚の「王道」とは遠いところにいるような。繰り返し登場する筆者の御贔屓、紅ゆずるさんと綺咲愛里さんの退団公演『GOD OF STARS—食聖—』(2019年/宝塚大劇場公演/主演 上記)も、とてもアツく楽しい少年漫画と少女漫画の間をいくような愉快な冒険譚だったが、あれを宝塚の王道と思う人はいないだろうと断言できる。
そんななか、この2020年、彼女の作品が初めて「宝塚の王道」と交わった。
それが、今回ねじ込んでまで彼女のことを書きたいと思った大きな理由であった。
『はいからさんが通る』(2017年梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ公演および2020年花組宝塚大劇場公演/いずれも主演 柚香光・華優希)。
大和和紀氏原作でアニメやドラマにも多数メディア展開され、名前だけでも聞いたことがあるという人は多いはずの少女漫画の金字塔とも言える作品だ。
主人公・花村紅緒は剣道と槍道が特技で酒乱という跳ねっ返りのじゃじゃ馬娘だが、祖母の代からの許婚という青年将校・伊集院忍との出会いを経て、反発しながらも惹かれ、戦争や震災を経て彼や取り巻く人たちとのつながりを通して成長していく女一代記的作品である。
この作品を宝塚で上演すると聞いた時、これまでに述べたような理由から「紅緒をタカラジェンヌが、しかも娘役がやるなんて」と少し嫌悪感を抱いたことをここに告白する。母親がロシア人であるという少尉(伊集院忍)が宝塚の男役スター的なビジュアルであること以外に親和性がないように見えたのだ。
自立して快活ではあるが、言葉を選ばずにいうなら下品でトラブルメーカーなヒロイン、作品解説に「容姿は普通」とまである。大和さんが描く可愛らしいイラストだからキュートなものを、3次元に近づけてしまって大丈夫か?醜くなりはしないか?
そんなもの、宝塚の娘役が演じる「女性以上に女性らしい愛らしさ」にフィットするのか、それが壊されるのではないかという不安—
そんな心配をよそに、見事に演じ切ったのがヒロインの華さんであった。
破天荒で無鉄砲な振る舞いの裏に、軍人の娘らしい凛とした面影。そもそも華さん自身が品をたたえているからどんなに暴れても下品に映らない。少女から未亡人、職業婦人に成長していく様子を豊かな声色で演じ分け、どんどん艶っぽくなっていく華さんの「紅緒」を、失礼ながら初めてこんなに魅力的なキャラクターだったのかと発見したほどだった。
そんな華さんが演じる紅緒を「ぼくだけのはいからさん」と愛し抜く少尉・柚香さんは持ち前のビジュアル以上に美しい。2次元の紙面では感じられないみずみずしく上気するような少尉の美しさを表現していた。
そしてそれは先天的に「浅倉南的」な宝塚の伝統的な娘役らしい華さんが紅緒を演じるからこそ生まれる化学反応だった。
私は長年宝塚歌劇を見ていて、今も昔も宝塚とはトップコンビのカップル芝居が持ち味だと思っているが、先のように「少年漫画的な男役中心のスターシステム」しか正解がないと思っていたことをこの公演を見て恥じたのである。
漫画やアニメの俯瞰した目線とは違って、少尉(男役トップスター)の目を通して見る「ぼくだけのヒロイン」(娘役トップスター)という主観的物語構造。
これは宝塚にしかできない2.5次元の翻案の仕方であり、宝塚は特殊で狂気的な仮想ジェンダーとはいえ少しずつ現代のジェンダー観に適応していかねばならないとしたら、これ以上の正解はないという魅力的な関係性のトップコンビだと思った。
現代的なジェンダー観に照らせば、男と女は寄り添いあうものではなくそれぞれ自立するべきだという。宝塚ファンの中にも「バレエ=オペラ型」の観客を中心に、それを宝塚のスターシステムにまで持ち込むべきだと声高に主張する人は正直増えている。
でも、こういう「神田川的な」肩を寄せ合う2人にしか描けない美しさって、まだ捨てたくない。むしろ、自分がゴリゴリに自立しているからこそ、こういうお互いにしかよすがのない関係性の儚さに自分の生き様が本当に正しいのかを省みることができるのでは?と思うのだけれど。
植田紳爾氏が『ベルサイユのばら』で男装の麗人を商品化することに成功したように、小柳さんは「新しい時代のトップコンビ像」を作り上げた。植田小柳両名に共通するのは、過去のシステムを壊して作り直すのではなく、“それまでの大切なエッセンス“を守るために変わるというところだと感じている。
小柳さんが描いた柚香さんと華さんのカップル芸は、まるで戦禍と震災を生き延びた少尉と紅緒のように、大切な宝塚らしさを守るために走り抜けて逃げるようだなと思った。
事実、自分の周りのたくさんの“古参ファン(ベルばら前後からファンをやっているお歴々の宝塚ファンのお姉さまがた)“は、彼女ら2人の様子に自分たちが少女の頃に見た昭和〜平成のトップスターコンビを投影し想いを馳せていた。
振り返れば、小柳さんが寄り添って「名作化」してきた作品の主演者たちは、いつも世間の“大きな声“に晒されてきた人のように思う。先行する人気に“実“を追いつけようと走り続けた柚希・夢咲コンビ、男役から娘役に転向したばかりの愛希さん、ビジュアルの美しさ以外の揚げ足をチクチクと取られ続けた紅・綺咲コンビ、早すぎるトップ就任と好奇の目に晒された星風さんと華さんなど。
よくよく考えればその子たちは皆「等身大のがんばる女の子」なのである。
パッと見、先天的に美しいとか肢体バランスに恵まれているとかいないとか、ファンから見て優遇されているとか冷遇されているとかによらず、宝塚ってそもそも全員が等身大の女の子たちの集まりなのだ。ついつい浮世離れした装置に目がいってそこを忘れがちになるけれど、実は宝塚って「等身大」の集合なのである。
あそこにいる子は全員、そして落ちた人間を代表して言わせてもらえば、あそこを目指してがんばらなかった子なんて少なくともこの40年ちょっとで1人もいないと断言したい。
そんな彼女たちの一番そばで、前々回の木村信司さんの「現実的な」視点での伴走の仕方とはちょっと違って、彼女たちの生き様をファンタジーにし続けるのが小柳奈穂子さん流。
「なんだか少女漫画のヒロインみたい!」「少年漫画のヒーローならこんな時どうするかな?」
小柳さんの伴走には、そんな楽しさと、一縷の厳しさが同居する。
あの狭くて閉ざされた箱の中で日々奮起する「少女」たちにとって、涙を花に変え、暗い空を切り裂いて飛んできてくれる人。
ポジティブなファンタジーの力で、普通の少女を皇妃に引き上げる魔法をかける。
実は、生徒(出演者)にとっても私たちファンにとっても、白馬の王子様は男役トップスターではなく、小柳さん自身なのかもしれないな。


























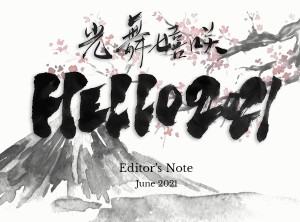


ななしましゅうこ/1986年生まれ、福岡県出身。立命館大学文学部学際プログラム(現・文化芸術専攻)卒業。某放送協会営業職を経て美容師の技術やデザイン、経営に特化した業界誌を発行する出版社K書房に勤務。総合誌・月刊B●B、書籍編集部経て会員制マネジメント誌編集部に異動。現在同部デスク。宝塚やジャニーズなどの「各種オタク」であることを認知されすぎて『ビジネスオタクではないか』と疑われるが、タカラヅカ受験経験アリ、上記ゼミ在学中の研究テーマは『シェイクスピアと宝塚/歌舞伎という上演装置』という筋金入り。趣味は、電車の中などで会った人のヘアスタイルを見てカット手順を脳内シュミレーションすること。宝塚鑑賞においてもヘアメイク技術はめっちゃ見る。ヅカから髪、盛大に公私混同が信条。
ブログ 『ヅカと、髪。』