生田大和 言葉より高精細
2021.02.18
宝塚歌劇は出演者が女性だけで構成される世界で唯一の劇団とされている。
だから、どんな男性の登場人物もすべて女性が演じるし、女性の人物もしかりだ。男性登場人物を演じる役者のことは「男役」というが、女性登場人物を演じる役者のことを「女役」とはいわず“娘役”という。サラッと「娘役の誰々さんが……」というようになったら、「宝塚沼」へ足を一歩踏み入れているといっていい。
宝塚の特性上、男性(現代社会では性別は男女2項ではないとされるが便宜上)ではありえないようなキザでカッコいい男役の魅力に人気が集まるため、スターシステムにおいて娘役は男役に次ぐ存在とされやすい。芝居でもショーでも、同じトップスターながら男役が主演で娘役は“その相手役“という位置づけになる。
この点に関して、よく現実社会と混同した考えで男尊女卑的だと批判したり、娘役の地位向上や自立を謳ったりする人が現れるが、宝塚というそもそも異常な装置の中での「仮想ジェンダー」は現実社会の絶対価値とは別の“あくまで2つだけに分断した性“の相対関係だと思うので、その是非に関する議論はここでは丁寧にスルーしておく。
某探偵漫画でいうところの「時計型麻酔銃で何発も麻酔を打ち込んでよいのか」という議論と同じだと個人的には思っている。
それを言い始めたら現代に“性”は存在しない。私たちは“それぞれの私”でしょう?と思うのだけど。
今回取り上げた生田大和さんは、そんな“それぞれの私”の描写が随一だと感じる作家だ。私は特に、その手腕を娘役の描写に対して強く感じ、非常に好きなのでぜひ紹介したい。
前回の小柳奈穂子さん回において、宝塚のスターシステムに本来フィットするのは少年漫画だという見解を書いた。その前提でいくと、娘役、特にヒロイン周りはえてして形骸的になるのがお約束であった。鉄板の「浅倉南型」「赤木晴子型」に始まり、多様性が出たとしても「歩美ちゃんと哀ちゃん」「ナミとニコ・ロビン」「サクラとヒナタ」と言った程度のバリエーションが関の山だ。これは別に男性向け漫画に限らず、森鷗外だろうがフィッツジェラルドやらトルストイやら、古来より男性が書いた文学は大体そんなもの。
宝塚は男性作家が多いことに加えて、さらに男役を主役に据える世界観で物語を紡いでいくので、どうしてもその例に漏れずにいた。ヒロインを「他者」として理想的に描写する形である。
それを、あくまで他者でありながらパーソナリティにフォーカスした書き分けをしているところが生田さんの持ち味のように感じる。また、この辺りを鮮やかに書ける人は一人目に紹介した故・柴田侑宏さんなど過去にも例がありはするのだけど、本当にこれは勝手なイメージで、言葉を選ばずにいえば「経験豊富そう」な印象がある人たちだった。たくさんの女を知っているのだろうな……カッコいいもんね……という感じ。知っているから書ける、知らないから書けない。もちろんそれはそれで悪いとは思わない、書けないことも。知らないことを無理やり書こうとするよりは、断然いい。
一方、これも言葉を慎重に選ぶんだけど、生田さんはものすごくイイ意味で「その匂い」が全くない。モテなそうとかそういう意味ではなく、匂いがニュートラルなのだ。先述の表現を繰り返せば“性がない“現代的な感じ。性よりも前に人を見ている感じがするのである。
やっと生田さんの経歴を紹介すると、2003年に大学卒業後すぐ宝塚歌劇団に入団。2010年に『BUND/NEON 上海』(花組宝塚バウホール公演/主演 朝夏まなと・白華れみ)で演出家デビュー。その後着実にヒットを重ね、2014年には早々に大劇場デビューを果たす。前々回の上田久美子さんと同じく、彼自身に信頼を寄せるファンも多い。
私が初めて彼の作品を見たのは『ランスロット』(2011年星組宝塚バウホール公演/主演 真風涼帆・早乙女わかば)だった。ランスロットとは中世ブリテンの騎士道物語「アーサー王伝説」に登場する人物で、主人公アーサー王の妃グウィネビアと密通し、円卓の騎士の不和を引き起こすきっかけを作った。よくよく考えるとその随分あとに観た『ひかりふる路』(2017年雪組宝塚大劇場/主演 望海風斗・真彩希穂)も、『鎌足』(2019年星組梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ公演/主演 紅ゆずる・綺咲愛里)も、主役として描かれづらい人にスポットを当てるものだった。
その傾向は、娘役という普段スポットが当たらない存在への緻密な人物描写に通じるところがありそうだ。
だが、最初に彼の『ランスロット』を見た私の感想はもちろんそこまでは至っておらず、最初に注目したのはヒロインであるグウィネビアを演じる役者二人の説得力だった。
1人の人生を長く演じる際、宝塚も他の芝居と同じように「幼少期」と「青年期」を別の人間が演じることは大いにある。ただ、宝塚の場合他の芝居と違って「マジもんの子供(子役)」がいないので、同年代の女子たちが「子供」と「大人」を演じ分けることになる。
この『ランスロット』におけるグウィネビア役は、主軸となる青年期を早乙女わかばさん、補完する幼少期を綺咲愛里さんが演じることとなった。ちょっと、画像が載せられないので二人の顔をググってほしいのだが、この二人の顔って本当に「綺咲愛里さんが大人になったら早乙女わかばさんになりました」という説得力がえげつないのだ。シャープな顎、通った鼻筋、綺咲さんの目は大きく垂れて下についているが成長するとやがて溌剌な明るい瞳の早乙女さんの顔立ちになってくる……。美容編集として専門的なことをいうとハチの張り方と前髪の生えグセもすごく近しい。
映像でも舞台でもある程度似た持ち味での配役を善処したいと思うのは本心としてはあると思う。だがそこに固執できないのが現実だ。しかも舞台作品の場合は遠景での表現だし、宝塚の場合先程述べたように「子役」はありえない上にスターシステムという配役の縛りがあるので、子役の方が大人役より大人っぽい顔、顔立ちとしては全く似ていないということも大いにありうる。
ちなみに、この「えげつない説得力」での配役は知る限りもう一度繰り返されており『春の雪』(2012年月組宝塚バウホール公演/主演 明日海りお・咲妃みゆ)で、主役の清顕役の青年期を主演の明日海りおさん、幼少期を海乃美月さんが演じる。この二人は細面で端正な顔立ちながら鼻から口元に非常に特徴がある。私はこの作品でそのことを再発見したとき、とても前向きな意味で「この人(生田さん)変態やな」と思った。
何かを極めるのに変態性って、つきものだと思うのだ。
生田さんは良い変態だと、このとき好感を持った。
さらに、この「幼少期の清顕」を演じた海乃さんは本来娘役なのだが、このことは後ほど回収するので覚えておいてもらいたい。
(※宝塚においては「子役」がいないので、小柄な娘役が「男性の幼少期=少年役」を演じることは多い)
そんなふうに、彼のことを「変態やな」と称えながら、タイトルに冠したように“高精細だ”と感じたのは、先述の『鎌足』であった。
中臣鎌足の一代記を描くこの作品で、彼を取り巻く主要どころの女性は計3人だ。
初恋の幼友達であり、権力への執着のきっかけになった車持与志古娘。彼女が今作におけるヒロインだ。
そして成果の“褒美“として与えられた采女で側室の安見児。そして、正妻とされる鏡女王を物語上から大胆にカットし、鎌足の幼友達だった蘇我入鹿を恋と権力の虜にし “討つ政敵”に身を落とした女性天皇・皇極帝にスポットを当てた。
義務教育レベルの知識でいうと、鎌足を描こうとするときにこの3人を彼の人生における主要メンバーとしてスポットを当てることは控えめに言って変態である。細かくは割愛するが、先述の「少年漫画のセオリー」に照らせば、宝塚的な悲劇のヒロインからすると鎌足の元に嫁いできた正妻の鏡女王でありそうなもので、与志古娘は歴史上では天智天皇と中臣鎌足の間でやりとりされた女の一人にすぎなく、安見児に関しては
「我はもや安見児得たり 皆人の得難にすといふ 安見児得たり」(万葉集巻第二95)
という、ストレートすぎるトンチキ短歌でしか残っていないほどの“男中心の歴史の脇役”であった。また、皇極帝と蘇我入鹿のロマンスは一般的には俗説の域を出ない。
作品中、与志古娘は何があっても誰の元に行っても鎌足を愛し抜くヒロインの肖像だった。まあこれはいい。
生田さんの真骨頂は、政治の一道具に過ぎなかった安見児の、知らない男の元に売られる恐怖や戸惑いと、彼女に対する鎌足の慈しみを丁寧に表現してみせたところ。そしてさらに、権力腐敗の象徴的な捉えられ方をする皇極と入鹿の密通を、頂に近づくほど孤独になり肩を寄せ合う男と女として描いたところ。
私は成績がいい方だったけれど、20年の時を経て初めて教科書に色がついて見えた。
特に皇極帝をしっかりと“女”として書くことは革新的だと思った。どんな人も本質は弱くて、恋をするのに理由や詭弁はいらなくて、それこそ強いのだという眩しさ。
想像がつかないような遠い人にも、人生があって、感情がある。
感情って正論やセオリーでは語れないもので、語れるとしたら経験か想像力によってだけだ。
余談だが、この皇極を演じた有沙瞳さんは生田さんの作品『伯爵令嬢』アンナ、『ドン・ジュアン』エルヴィラと、ヒロインに対峙する主要人物を鮮やかに演じてきた娘役である。彼女は生田さんのミューズなんだろう。
私の好きな宝塚の座付は、いつもそうやって何かしら生徒(演者)と近いところに心を置いて居る。
歴史も、役も、目の前の生徒も、細胞一つまで描き切る。それが生田さんの筆致である。
最後にもう一つ、私が強烈に生田さんのファンになった作品を文脈無視でプレゼンして締めくくりたい。それは、前述の『春の雪』である。映画化もされている三島由紀夫の小説『豊饒の海』4部作のうちの第一作目であり、「奔馬」「暁の寺」「天人五衰」と続いていく。そのうちの「春の雪」は明治末期の皇族・華族を中心とした登場人物たちの中で、侯爵家の清顕とその幼馴染でありクライマックスでは宮家からの勅許を賜る美しい華族の娘・聡子の不器用な恋模様を中心に展開していく。4部の中では一番宝塚的作品といえた。
とはいえ、三島文学というのは普通に展開するには思想が強すぎるし、だからといって思想を削ぎ落とすと、清顕と聡子のもどかしい恋路は懐かしの「ケータイ小説」になってしまう。
そこで生田さんがやったのは、清顕と聡子の恋模様にだけピントを当てたまま「奔馬」も「暁の寺」も「天人五衰」も全部包括して“ヅカ版春の雪=豊饒の海“にしてしまおうということだったと私は読んでいる。
その企みに気づいてゾッとしたのは、クライマックスのこのセリフだった。清顕の子を宿してしまったことで思い悩んだすえに仏門に入った聡子に対し、清顕の親友の本多がなんとか清顕会ってくれないかと懇願する場面だ。
聡子 その松ケ枝清顕さんという人はどういうお人やした?
私は「ん?」と思った。原作にそんなシーンもセリフもないのである。
で、見つけたのが4部作ラストの「天人五衰」。『豊饒の海』シリーズは、この清顕の親友・本多が老年まで清顕の“生まれ変わり“の存在を追いかけながら生きていく物語なのである。
晩年の本多が聡子を訪ねるシーンのセリフを「春の雪」の世界にねじ込んだ。長い月日を経た老年期でなく、ついぞ昨日まで愛した男を突然忘れさせるという絶望的な描写は、清顕が聡子に対して犯した罪や残した情念を4部もかけずに一気に裁くぞという気迫すら感じられた。
そして、やっと回収する「清顕の幼少期」を演じた人、海乃美月さんについて。
彼女は作品中もう一役担当していた。清顕の親友・本多の従姉妹であり、彼が初めて恋する女性・房子。10代の男らしい、理由のない衝動的な恋の相手が房子だった。
この海乃さんの二役に気づいたとき、生田さんはこの「ヅカ版春の雪」は本多を主軸に、相手役を清顕とした「清顕の面影を追う豊饒の海」に仕立てているのだと思った。儚くて身勝手で、それなのに美しくて抱きしめたくなるような明日海りおさんの清顕は、冒頭で例を出したような“男目線の古典文学“でいえば確かに主人公のファムファタル(運命を左右する女性)かもしれない。そう読むと、クライマックスでこの座組中の二番手男役スター・珠城りょうさん演じる本多の腕の中で生き絶える主演男役スター・明日海さんの清顕の姿に、強い「説得力」が加わった。
たった2項しかない宝塚世界の仮想ジェンダーで、そのスターシステムに基づいた世界を物語上は厳正に保ったままで、男役を相対的な存在として翻弄し、娘役に絶対的な主導権を与えられた座付は、知る限り彼一人だと思う。
それが自由で柔軟だから、彼の作風は経験則を感じないのかもしれない。男と女というたった2つのラベルだけでも、人はこんなに自由なんだと感じられて、生田作品の多くは眩しいくらい鮮やかで無限だ。
宝塚は男役と娘役という2つの仮想ジェンダーで成り立つために、概ね物語の主題が異性愛である。悲恋だろうが純愛だろうが不貞だろうが、そういう恋模様に一喜一憂する少女の気持ちで観客は物語世界を堪能するし、その観客には私のような「元少女」だけでなく「マジもんの少女(子供)」も少なくない。
そんな“異常でニッチなのに子供にもひらけたコンテンツ“だからこそ、恋模様が高精細であることはものすごく意味のあることだ。女性の権利にはじまり、性の多様性やハラスメントが取り沙汰されることが多いが、すべての問題の根幹は「人と人との感情」のはずだからだ。
目で追った、手が触れた、抱きしめた……という延長の肉体的なコミュニケーションの正当性の根拠はすべて「恋」のはずなのである。それが曖昧だと、すなわち「罪」だ。
徐々に死語になりつつはあるが壁ドンしかり萌えしかり、その前提をすっ飛ばした表現が多い日本カルチャーではあるが、宝塚はあくまで「花街(性だけの世界)から一線を画する老若男女の娯楽」であったはずなので……と、苦言を飲み込みつつ見る“今っぽい“作品が宝塚内に横行している現実もある。
そんな中で、すべての愛し合う行為、憎み合う行為を細胞や遺伝子、運命の歯車一つひとつまで執着し、脚本上の言葉尻だけでなく演者一人ひとりの容姿から成り立ちまで抉り出して高精細に描きだす生田さんの“変態性“は、逆に生徒(出演者)や観客の多くを占める女性の尊厳を守る。
尊くて失いたくない狂気的な良心だと感じてならない。


























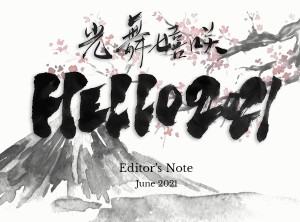


ななしましゅうこ/1986年生まれ、福岡県出身。立命館大学文学部学際プログラム(現・文化芸術専攻)卒業。某放送協会営業職を経て美容師の技術やデザイン、経営に特化した業界誌を発行する出版社K書房に勤務。総合誌・月刊B●B、書籍編集部経て会員制マネジメント誌編集部に異動。現在同部デスク。宝塚やジャニーズなどの「各種オタク」であることを認知されすぎて『ビジネスオタクではないか』と疑われるが、タカラヅカ受験経験アリ、上記ゼミ在学中の研究テーマは『シェイクスピアと宝塚/歌舞伎という上演装置』という筋金入り。趣味は、電車の中などで会った人のヘアスタイルを見てカット手順を脳内シュミレーションすること。宝塚鑑賞においてもヘアメイク技術はめっちゃ見る。ヅカから髪、盛大に公私混同が信条。
ブログ 『ヅカと、髪。』